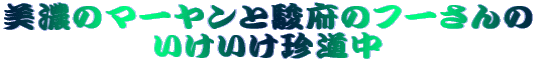|
|
 |
俺んちの写真は数多くあるが、写真のパターンが一緒である・・・缶ビールを持っている写真、コンパニオンと歌を唄うか、側に寄り添っている写真が多い・・・頼んでもいないのに、シャッターチャンスは酒、おなごがつきモンである。顔は怒っているのが少ないだけいいんじゃないかと思うのだ・・・
デジカメで人の写真を撮ることはできても、自分の写真は写せない、今の写真はスタイルも顔も崩れてきて、写真栄えがしないからいいかもしれないが、少し寂しい・・・昨年久しぶりに馬籠に行ってきました。
37〜8年ぶりに行ってみると面影は残っているものの道路なんかが変わっていて別のとこにきた感じがしました。 しかし宿場のある通りに入るとタイムスリップしたかのように昔の面影がよみがえってきたのです。昨年から長野県山口村から岐阜県中津川市と合併になる。 |
|
|
|
|
一里塚・・・旅の行程の目安として4kmごとに道路の脇に土を盛って塚を築いた物で馬籠宿と落合宿の境に今も残っている。
桝形・・・・宿場の入り口に道路を直角に2度曲げた物、軍事的な目的を以て作られた。 高札場・・村人や旅人に法令を徹底さける手段として設けられたもので、宿場の入り口にある(復元) 本陣、脇本陣・・公儀の旅に備え宿泊、休憩のための施設として宿場には必ず設けられた(遺構)中山道は江戸日本橋を起点とし京都まで約530kmの道路で、ここには69箇所の宿場がおかれていた。
東海道の504kmに比べ遠回りではあったが、東海道には大井川の川止めをはじめ海の旅や川越などの危険が伴った。 中山道69宿のうち木曽には11の宿場があり、馬籠宿は板橋を1番目とすると43番目になり、江戸からの距離は332kmになる。
道路が南北に貫通しているが急な山の尾根に沿っているので、急斜面で、その両側に石垣を築いては屋敷を造る「坂のある宿場」である。 ・山の尾根のため水に恵まれておらず、火災が多いのが特徴である。
|
 |
|
|
|
|
 |
・馬籠の町並みは1895年(明治28年)と1915年(大正4年)の大火で、古い町並みの建物のすべてを消失し、宿場独特の家並み風景は見ることが出来ない。
そのような中で、若い人たちの間から、「地域の将来に対する基本計画すらない中で、観光客の自然増だけに頼る今の姿のままでいいのか」といった危機感が深まってきた。
このため1983年(昭和58年)、観光協会内に「町並み保存委員会」が発足し、町並みの景観整備の検討に着手した。そしてその診断を環境文化研究所(所長太田博太郎氏)に依頼することとなった。 診断は観光協会の費用で予備調査に着手し、翌年度には山口村によって本調査を実施した。
診断の結果「中山道フィールド博物館構想」が提案された。 街道そのものを自然の博物館とする発想に基づくもので、岐阜県境から妻籠宿に至る間の中山道およびその周辺の環境を整備し、観光客がこの街道を歩くことに意義を持たせるというものである。
|
|
|
|
近くに富士見台、湯舟沢、妻籠があり、岐阜県と長野県の県境には情緒豊な名所があります。
飛騨の高山とは一味違った趣のあるところです。
中津川市は根ノ上高原、付知峡、付知川など自然豊な地形で、お隣の恵那市には恵那峡、博石館、大正村、女城主岩村、寒天の山岡、蜂の子の串原、モンゴル村の上矢作、阿木川ダムなどそれぞれの町が個性をだして、全国に発信しています。 |
 |
|
|
| 34 |
| 次へ |
|