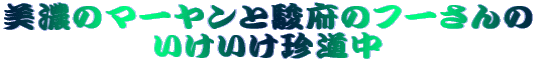|
|
 |
妻籠宿は中山道と飯田街道の分岐点に位置し、古くから交通の要所として栄えた。昭和43年に町並みの保存が始められ、昭和51年に国の重要伝統建造物保存地区に選定される。
全長約500mの町並みは、江戸時代にタイムスリップした感じで、どれも当時の面影を残し、懐かしさと郷愁を感じる情緒いっぱいの宿場町。
妻籠宿本陣
江戸時代、大名など身分の高い人が宿泊した本陣、最後の当主だった藤村の兄、島崎広助が東京に出たため明治20年代に建物は取り壊された。
現在の建物は1995年建築のもので、江戸時代の間取り図をもとに忠実に復元されたもの、石置き屋根に当時のようすが偲ばれる
|
|
|
|
|
|
脇本陣奥谷
歴史資料館、妻籠宿本陣を併せた南木曽帳町博物館にある妻籠宿の脇本陣。庄屋、問屋を代々務めた林家の旧宅を資料館として公開。説明を聴きながら約20分で見学が出来る。藤村の初恋の人で後に林家に嫁いだおゆふさんの愛用品や、絶筆となった藤村の貴重な資料を展示。
上嵯峨屋
町並み保存運動として建物の解体復元が行われて来た妻籠宿。上嵯峨屋もその一つで江戸中期に庶民の木賃宿として使われていた建物を昭和44年に解体復元したもの建物中央に土間が通る中土間形式というめずらしい造りが特徴な、貴重な造りの上嵯峨屋。また北に100mくらい進むと見えてくるのが下嵯峨屋。江戸時代の庶民の住宅で当時の生活道具も展示されている。
|
 |
|
|
|
|
 |
馬籠峠
馬籠宿と妻籠宿の間に位置する標高801mの峠。馬を引いて越える事が出来ないほど険しい道のりだったことからこの名前となる。
現在の峠道は檜林の中の快適な信濃路自然遊歩道として整備。明治24年に峠越えをした正岡子規の句碑や吉川英二の小説「宮本武蔵」に登場する男滝、女滝。江戸時代に木材が木曽から外に出ないように監視していた番所跡などのみどころをめぐりながらハイキングが出来る。
歴史の道・中山道
妻籠宿から大妻籠、馬籠峠を経て馬籠宿に至る中山道は、木曽路でもとくに往時をしのばせるエリア。歴史を伝える木漏れ日の道が、静かに旅人を迎えてくれます。 |
|
|
|
|
宿駅が制定されると妻籠宿本陣には島崎氏が任命され、明治に至るまで本陣、庄屋を兼ね勤めました。島崎藤村の母の生家であり、最後の当主は藤村の実兄で、馬籠から伯父の所へ養子にきた広助(ひろすけ)でした。
本陣は明治に入り取り壊され、その後明治32年に御料局妻籠出張所が建設されました。
本陣の復原は妻籠宿の保存が始まった当時からの念願であり、島崎家所蔵の江戸後期の絵図をもとに、平成7年4月に復原されました。
南木曽町博物館は、この妻籠宿本陣と脇本陣奥谷、歴史資料館との三館により構成され、共通券で見学できます。
|
 |
|
|
| 35 |
| 次へ |
|